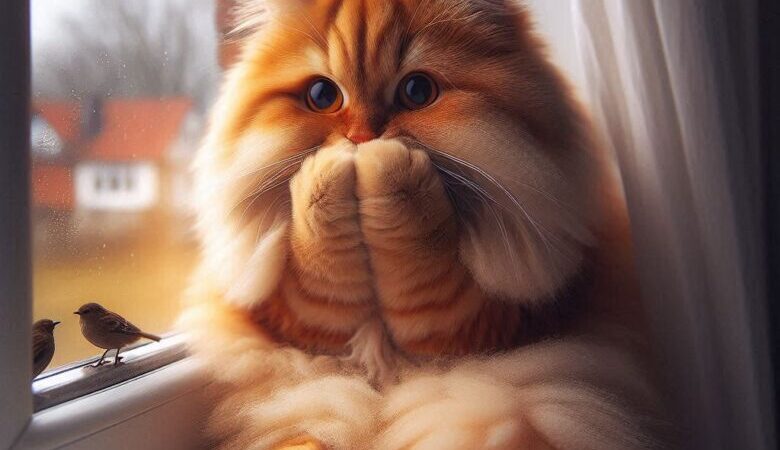

「愛猫がまた餌を吐いてしまった…」そんな経験はありませんか?猫が餌を吐く原因は様々で、飼い主さんにとってはとても心配なことです。この記事では、猫が餌を吐く原因から、具体的な対策、そして動物病院へ連れて行くべきサインまで、わかりやすく解説します。
愛猫の「なぜ?」「どうして?」「どうすればいいの?」という疑問に答え、愛猫の健康を守りたい飼い主さんのための情報を満載しました。この記事を読めば、愛猫が餌を吐く原因が理解でき、適切な対処法がわかります。愛猫の健康を守るために、ぜひ参考にしてみてください。
クリックできる目次
1. 猫が餌を吐く原因
1. 早食い
猫はもともと早食いをする習性があります。特にドライフードは水を吸って胃の中で膨らむため、胃を圧迫し、吐き出す原因になります。
餌を丸呑みすることで胃に負担がかかり、吐き戻しが起こることがあります。
多頭飼いの場合、他の猫に餌を取られまいとして急いで食べることがあります。この早食いによって、食べたものがきちんと消化される前に胃から吐き戻されることがあります。

2. 食事量の過多
一度に多すぎる量の餌を食べると、猫の胃が過度に膨張し、吐き戻しを引き起こす可能性があります。
3. 食事内容の急な変更
猫の消化器系は敏感です。餌の種類を急に変えると、猫の胃腸が適応できず、不調を引き起こし、吐く原因となることがあります。
4. 毛玉

猫は毛づくろいを頻繁に行うため、多くの毛を飲み込んでしまいます。この毛が胃にたまり、毛球と呼ばれる塊になると、吐き出すことで体外に排出しようとします。特に長毛種の猫は毛玉を吐きやすく、季節の変わり目など、毛が多く抜ける時期にこの現象がよく見られます。
5. 食物アレルギーや不耐性
猫が特定の食材にアレルギーを持っている場合、嘔吐をすることがあります。
例えば、魚や乳製品が原因で消化不良やアレルギー反応を引き起こし、嘔吐することがあります。
6. 異物の誤飲
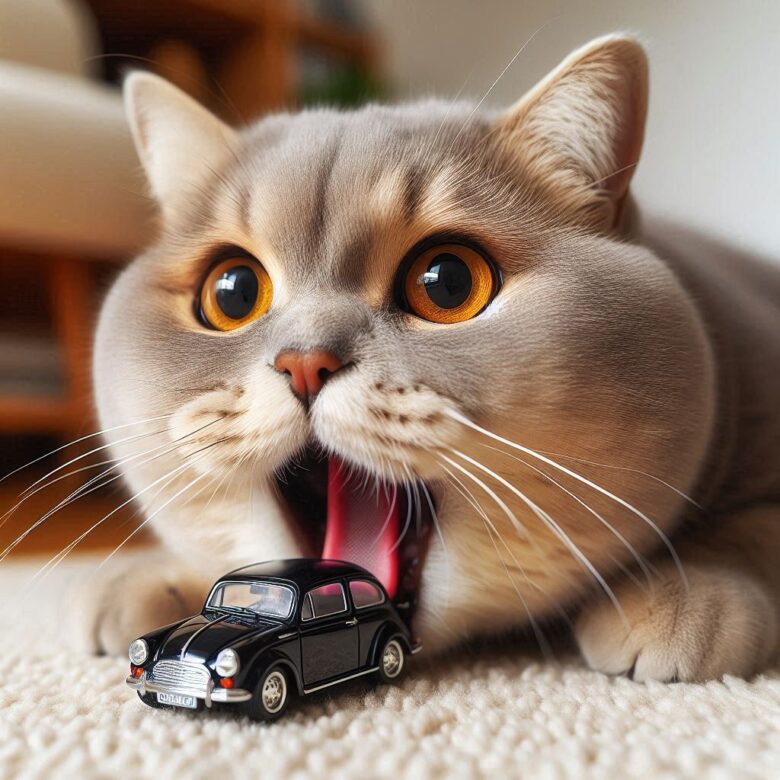
好奇心旺盛な猫は、おもちゃや植物、糸やゴムなど、食べるべきでないものを誤って飲み込むことがあります。これが胃を刺激して吐き気を引き起こす可能性があります。
7. 感染症や疾患
胃腸炎やウイルス感染、また腎臓病や糖尿病、甲状腺機能亢進症などの慢性疾患が、吐き気の原因となることもあります。
8. ストレス
環境の変化や大きな音、新しいペットの導入などが原因で、猫はストレスを感じて吐くことがあります。
例えば、引っ越しや新しい家族の登場など、猫にとっての大きな環境の変化がストレスとなり、嘔吐を引き起こすことがあります。ストレスは猫の消化器官にも影響を与えるため、注意が必要です。

9. 便秘
便秘が原因で消化不良を起こし、嘔吐することがあります。
猫が便秘になると、消化器官に負担がかかり、餌を消化しきれずに吐き戻してしまうことがあります。便秘は食事や水分摂取の不足、運動不足などが原因で起こります。
2. 猫が餌を吐く時の対策法
1. 早食いへの対策
- 餌を小分けにして与える: 一度にたくさん食べさせるのではなく、少量を複数回に分けて与えることで早食いを防ぎます。
- 早食い防止フードボウルを使用: 特殊な形状の食器で、猫がゆっくりと食事できるように工夫されています。
- フードの種類:ドライフードを水でふやかしたり、ウェットフードに切り替えることで、ゆっくりと食事することができます。
- 多頭飼いの場合は別々の場所で給餌:猫ごとに別の場所で餌を与えることで、競争心による早食いを防ぎます。

“ウェットフードおいしいにゃ。ゆっくり食べられるから満足感もアップにゃ!”
2. 食事量の過多への対策

- 適切な量を測って与える: 猫の年齢、体重、活動量に応じた適切な食事量を守ることが大切です。過食にならないように餌の量をコントロールしましょう。
- 餌の回数を増やす: 1回に与える量を減らし、1日に複数回与えることで、胃に負担をかけずに消化を助けます。
- 定期的な体重測定:過剰給餌を避けるため、月1回程度の体重測定を行います。
3. 食事内容の急な変更への対策
- 段階的な切り替え:新しい餌に切り替える際は、1週間から10日かけて徐々に新しい餌の割合を増やします。例:1-3日目(旧75%:新25%)、4-6日目(旧50%:新50%)、7-9日目(旧25%:新75%)、10日目(新100%)
- 消化に優しい食事の選択:敏感な胃腸の猫には、消化しやすい食事を選びます。

“最初は戸惑ったけど、こうやって少しずつだと安心して食べられるにゃ。”
4. 毛玉への対策
- 定期的なブラッシング: 定期的にブラッシングすることで、猫が飲み込む毛の量を減らすことができます。特に長毛種は毎日ブラッシングをします。
- 毛玉対策用のフードを与える: 特別に配合されたフードやサプリメントは、毛玉の排出を促進し、嘔吐を減らします。
- 猫草: 猫草を食べることで、胃の中にたまった毛を吐き出しやすくなります。
5. 食物アレルギーや不耐性への対策

- アレルゲンを避けたフードに変更: 獣医師のアドバイスを受け、アレルギーの原因となる食材を含まないフードを選びましょう。
- アレルギー検査を実施: どの食材が原因なのか分からない場合は、獣医師に相談し、アレルギー検査を行い、正確な対応を取ります。
6. 異物の誤飲への対策
- 誤飲を防ぐための環境整備: 小さなものや危険な植物は猫の手の届かない場所に保管し、猫が誤って飲み込まないようにします。
- おもちゃの選び方: 誤飲のリスクが少ない安全なおもちゃを選びます。
- 異物が見つかったら獣医師に相談: 異物が確認された場合や嘔吐が続く場合は、すぐに動物病院へ行きましょう。
7. 感染症や疾患への対策

- 定期的な健康診断: 予防のためにも年に1〜2回の定期検診で獣医師の診察を受け、病気の兆候を見逃さないようにします。
- 異常があればすぐに相談: 嘔吐が頻繁に起こったり、異常が見られた場合は早急に獣医師の診察を受けましょう。
8. ストレスへの対策
- ストレスを軽減する環境を整える: 猫にとって快適で安全な高い場所や隠れ家を用意し、ストレス時に逃げ込める場所を作ります。
- 安心できる空間の提供: 猫がリラックスできる場所を作ることが、ストレス軽減に効果的です。
- 遊びの時間: 毎日、十分な遊びの時間を作ってあげます。
- 環境エンリッチメント:おもちゃや爪とぎなど、ストレス解消のためのアイテムを用意します。
- フェロモン製品の使用:猫用のフェロモン製品を使用し、リラックスできる環境を整えます。

「隠れ家があると安心するにゃ~。」
9. 便秘への対策
- 水分補給を促進: 十分な水分を摂ることが便秘予防に効果的です。新鮮な水を常に用意し、水飲み場を複数設置します。ウェットフードを取り入れ、食事からの水分摂取も増やします。
- 運動を増やす: 運動不足は便秘の原因となるため、日常的に運動させる環境を整えます。遊びを通じて適度な運動を促し、腸の動きを活発にします。
- 食物繊維: 食物繊維が豊富なフードを選ぶことも効果的です。

3. 猫が餌を吐いた時にチェックすべきポイント
猫が餌を吐いたとき、ただ単に「また吐いている」と思うのではなく、状況を観察することが重要です。吐く頻度や状況に応じては、病院に行く必要がある場合もあります。以下のポイントを確認し、猫の健康状態を把握しましょう。
1. 嘔吐物の状態
なぜ確認が必要か: 嘔吐物の内容物は、原因や対策を判断するための手がかりになります。例えば、毛玉が含まれていれば毛玉が原因かもしれませんし、食べたばかりの餌がそのまま出てきたなら早食いや消化不良が疑われます。
チェックする点:
- 未消化のフード: 早食いや食べすぎが原因かもしれません。
- 毛玉: 毛づくろいによる毛球が溜まっている可能性があります。
- 異物: 誤飲したものが含まれている場合、危険なので獣医師に相談する必要があります。
- 色: 嘔吐物の色も重要です。透明や白い泡は胃液の可能性、黄色や緑色の場合、胆汁が混じっている可能性があります。赤色や茶色で血液が混じっている可能性のある場合は、すぐに獣医師に相談してください。
- 匂い: 異常に強い匂いがする場合は、消化器系の問題が疑われます。

「未消化のフードが出てきたら、早食いが原因かも?」
2. 吐いたタイミング
なぜ確認が必要か: 吐いたタイミングを知ることで、何が原因かを絞り込むことができます。食後すぐに吐く場合と、数時間後に吐く場合では原因が異なる可能性があります。
チェックする点:
- 食後すぐか: 早食いや食べすぎ、あるいは食べ物が胃に合わない場合が考えられます。
- 数時間後か: 消化不良や腸の問題、感染症などが原因かもしれません。
- 特定の状況で吐くか: ストレスを感じた後や、運動後に吐く場合も原因を探る手がかりになります。
3. 吐いた後の様子

なぜ確認が必要か: 嘔吐した後の猫の行動や様子を観察することは、健康状態を把握する上で重要です。元気にしているなら心配はいらないことが多いですが、元気がない場合は早めの対処が必要です。
チェックする点:
- 元気かどうか: 吐いた後も元気に走り回っている場合、軽度の問題であることが多いです。
- ぐったりしているか: 吐いた後にぐったりしている場合は、重篤な病気の可能性があるので早急に病院に行くべきです。
- 行動の変化: 吐いた後に異常な行動(隠れる、鳴き続けるなど)が見られる場合も注意が必要です。
- 食欲や水分摂取: 食欲がない、または水を飲まない場合、身体に何らかの異常があるかもしれません。
4. 吐いた回数
なぜ確認が必要か: 嘔吐の回数も健康状態の指標となります。一時的なものなのか、慢性的な問題なのかを判断するために重要です。
チェックする点:
- 一度だけか: 一度だけの嘔吐で、その後元気なら心配はいりません。
- 繰り返しているか: 短期間に何度も吐く場合は、胃腸のトラブルや感染症、異物誤飲などが原因である可能性があります。特に1日に何度も吐くようなら、すぐに動物病院へ行くことが必要です。

「あれ、何度も吐いてるニャ…ちょっと不安かも。」
5. その他の症状
- 下痢や便秘: 吐くと同時に下痢や便秘が見られる場合は、消化器系の問題が疑われます。
- 体重減少: 体重が減少している場合は、栄養が十分に摂取できていない可能性があります。
- 発熱: 体温が高いように感じるか。
- 痛みのサイン: お腹を触られるのを嫌がるか。うずくまっているか。
- 呼吸の状態: 呼吸が荒くなっていないか。咳、くしゃみ、目やになどの呼吸器系の症状はないか。
- 脱水症状: 皮膚の弾力低下、目の凹みなどはないか。
6.その他の要因

- 最近の環境変化: 新しい食事や間食を与えたか 。新しいおもちゃや植物を家に入れたか。引っ越しなど大きな環境の変化があったか。家具の配置や家族構成に変化があったか。大きな音や見知らぬ人の出入りなど、ストレスになる出来事はなかったか。
- 異物摂取の可能性: おもちゃや小物が無くなっていないか。植物をいじった形跡はないか。
- ワクチン接種や投薬の状況: 最近ワクチン接種を受けたか。現在服用中の薬はあるか。
- 外出の有無(外猫の場合): 最近外出したか。何か変わったものを食べた可能性はないか。
- 多頭飼いの場合: 他の猫にも同様の症状が見られるか。
4. 動物病院に行くべき危険な嘔吐と疑われる病気
1. 頻繁な嘔吐
- 疑われる病気: 慢性胃腸炎、胃腸閉塞、寄生虫感染
- 説明: 猫が1日に何度も吐く場合や、数日にわたって嘔吐が続く場合、これは胃腸系の深刻な問題を示している可能性があります。特に、食べ物や飲み物を受け付けなくなり、脱水症状が見られる場合は緊急です。
2. 血液を伴う嘔吐
- 疑われる病気: 胃潰瘍、腫瘍、異物摂取による内出血
- 説明: 血液が混じった嘔吐は非常に危険です。赤い血液の場合は胃や食道の出血が疑われ、暗赤色や黒っぽい場合は消化器官の奥の出血が原因であることがあります。このような場合はすぐに動物病院に連れて行く必要があります。

「血が混ざってるなんて、これは普通じゃないニャ!」
3. 異物を吐く
- 疑われる病気: 異物誤飲による腸閉塞
- 説明: 猫がひも、プラスチック、その他の異物を吐いた場合、まだ体内に残っている可能性があり、腸閉塞などの危険が伴います。異物誤飲が疑われる場合も早急に病院で診察を受けるべきです。
4. 泡や透明な液体を吐く
- 疑われる病気: 急性膵炎、腎不全、胃腸障害
- 説明: 泡状や透明な液体を吐くことは、胃に何もない状態での嘔吐を示している場合があります。これが続く場合は膵炎や腎臓の問題が原因となっている可能性があります。
5. 緑色や黄色い胆汁を吐く
- 疑われる病気: 胆管閉塞、肝臓疾患
- 説明: 胆汁の色が混じった嘔吐は、胆管や肝臓の問題を示している可能性があります。この場合も迅速に獣医の診察が必要です。

「これ、胆汁ってやつかニャ…早く見てもらわなきゃ!」
6. 体重減少や脱水を伴う嘔吐
- 疑われる病気: 腎不全、肝不全、糖尿病、腫瘍
- 説明: 嘔吐に加えて急激な体重減少や脱水症状が見られる場合、内臓の疾患や腫瘍が進行している可能性があります。こうした症状が見られたらすぐに動物病院で検査を受けるべきです。
7. 突然の激しい嘔吐
- 疑われる病気: 中毒
- 説明: 猫が急に激しく嘔吐し始めた場合、毒物を摂取した可能性があります。特に人間の薬品、植物、殺虫剤などが原因となることがあり、即座に治療が必要です。
これらの症状や病気の可能性がある場合、素早い対応が猫の命を救う可能性があります。自己判断は避け、迷った場合はすぐに獣医師に相談しましょう。
ペット保険への加入も検討してみてください。突然の病気やケガの際の経済的な負担を軽減し、必要な治療を躊躇なく受けられるようになります。
猫は痛みや不調を隠す傾向があるため、些細な変化も見逃さないよう注意深く観察し、適切なケアを心がけましょう。

5. 猫が吐いた後の食事法・注意点
1. 嘔吐直後の絶食
2. 水分補給の注意
- 説明: 嘔吐が続くと脱水のリスクが高まるため、少量の水を提供することが重要です。ただし、大量の水を一度に与えると再び吐く可能性があるため、少量ずつ頻繁に与えることが理想的です。氷を舐めさせるのも効果的です。嘔吐が続く場合や猫が水を受け付けない場合は、獣医師に相談する必要があります。

「少しずつ水を飲むのがいいにゃ!」
3. 少量で消化の良い食事
- 説明: 嘔吐後、最初の食事は少量で、消化の良いフードを与えましょう。ウェットフードや、獣医師から推奨された消化に優しい特別な療法食が良い選択肢です。最初はほんの少し(ティースプーン1杯ほど)与え、猫の反応を見ながら徐々に量を増やします。
また、室温に近い温度の食事を与えましょう。冷たすぎる食事は胃腸に負担をかける可能性があります。
4. フードの種類を変更しない
- 説明: 猫が吐いた後でも、急にフードの種類を変えることは避けた方がよいです。新しいフードにより胃腸が刺激される可能性があるため、少なくとも数日間は普段与えているフードの中から消化の良いものを選ぶ方が無難です。
5. 複数回に分けて少量ずつ与える

- 説明: 嘔吐後の食事は、1日を通して4〜6回に分けて少量ずつ与えることがポイントです。胃腸に負担をかけないようにしながら、栄養を徐々に補給していくことで回復を促します。
6. ゆっくりと通常の食事に戻す
- 説明: 1~2日かけて、少しずつ通常の食事量に戻していきます。いきなり元の食事量に戻すと再び胃腸が負担を受け、嘔吐が再発する可能性があるため、注意が必要です。
7. 吐き気止めや療法食の活用
- 説明: 嘔吐が頻繁に起こる場合、獣医師に相談して吐き気止めの処方を受けることや、長期的に消化に優れた療法食を検討することが考えられます。猫の健康状態に合った食事管理が必要です。

「また吐かないように、ちゃんとしたご飯を食べるニャ…」
8. 症状の再発に注意
- 説明: 嘔吐が再発する場合や、嘔吐以外にも異常な症状(元気がない、食欲不振、下痢など)が見られる場合は、速やかに動物病院に相談してください。単なる胃腸の不調でなく、深刻な病気が隠れている可能性もあります。
9. 適切な食器と環境整備
- 説明: 嘔吐後、食器や食事場所がストレスになっていないか確認します。食器が不衛生であったり、食事場所が落ち着かない場合、猫が再び食べるのをためらうことがあります。清潔な食器を使い、猫が安心して食事できる環境を整えることが大切です。
6.よくある質問

Q1: 猫が時々吐くのは普通のことですか?
A: 猫が時々吐くことは珍しくありませんが、頻繁に吐く場合は注意が必要です。月に1〜2回程度の嘔吐は多くの猫で見られますが、週に複数回吐く場合は獣医師に相談しましょう。
Q2: 猫が吐いたらすぐに病院に連れて行くべきですか?
A: 以下の症状が見られる場合は、すぐに動物病院を受診しましょう:
- 頻繁な嘔吐(1日に複数回)
- 血液や胆汁を含む嘔吐
- 嘔吐に加えて元気がない、食欲がない
- 下痢を伴う嘔吐
- 急激な体重減少
それ以外の場合は、24時間様子を見て改善しない場合に受診を検討してください。
Q3. 猫が黄色や緑色の液体を吐いたのですが、これは何ですか?
A: 黄色や緑色の液体は、猫の胆汁である可能性があります。胆汁の嘔吐は、空腹が長く続いたり、胃腸の問題がある場合に見られます。頻繁に吐くようであれば、獣医師の診察が必要です。
Q4. 血が混じった嘔吐を見つけた場合、どうすればよいですか?
A: 血液が混ざった嘔吐は非常に危険な兆候です。内出血や胃の損傷などが原因の可能性があり、すぐに動物病院で診察を受ける必要があります。
Q5. 猫がしょっちゅう泡を吐くのですが、これは何を意味しますか?
A: 泡を吐くのは、胃に何も入っていない状態で嘔吐が起こることが原因です。頻繁に起こる場合は、胃炎や膵炎などの病気が疑われますので、獣医師に相談してください。
Q6: どのような食事が猫に適していますか?
A: 吐きやすい猫には、低脂肪で消化しやすい食事が適しています。食事を小分けにして与えることで、消化不良を防ぐことができます。
Q7: 猫が吐いた後の食事はどうすればいいですか?
A: 猫が吐いた後の食事は以下のように対応しましょう:
- 12〜24時間程度の絶食
- 水分補給を優先(少量ずつ与える)
- 消化の良い軽食から始める(茹でた鶏肉など)
- 徐々に通常のキャットフードに戻す
- 少量ずつ頻繁に与える
Q8: 猫の嘔吐を予防するにはどうすればいいですか?
A: 猫の嘔吐を予防するには以下の点に注意しましょう:
- 適切な量と回数での食事
- 定期的なブラッシング
- ストレス軽減(快適な環境づくり)
- 定期的な健康診断
- 適切な寄生虫対策
- 食物アレルギーの原因となる食材の回避
7.まとめ

猫が餌を吐く原因と対策
1.早食い
原因: 猫は早食いの習性があり、ドライフードが胃で膨らむことで吐き戻しが起こることがあります。また、多頭飼いの場合は競争心から早食いになることも。
対策:
- 餌を小分けにして与える
- 早食い防止フードボウルの使用
- ドライフードを水でふやかす
- 多頭飼いの場合は別々の場所で給餌
2.食事量の過多
原因: 一度に多くの餌を食べると胃が膨張し、吐き戻しを引き起こすことがあります。
対策:
- 適切な量を測って与える
- 餌の回数を増やす
- 定期的な体重測定
3.食事内容の急な変更
原因: 急に餌の種類を変えると、猫の胃腸が適応できずに吐きやすくなることがあります。
対策:
- 段階的な切り替え
- 消化に優しい食事の選択
4.毛玉
原因: 猫が飲み込んだ毛が胃にたまり、毛球となって吐き出すことがあります。
対策:
- 定期的なブラッシング
- 毛玉対策用のフードやサプリメントの使用
- 猫草の提供
5.食物アレルギーや不耐性
原因: 特定の食材にアレルギー反応を示し、嘔吐を引き起こすことがあります。
対策:
- アレルゲンを避けたフードに変更
- アレルギー検査の実施
6.異物の誤飲
原因: 猫が誤って異物を飲み込み、胃を刺激して吐き気を引き起こすことがあります。
対策:
- 環境整備とおもちゃの選び方
- 異物が見つかった場合は獣医師に相談
7.感染症や疾患
原因: 胃腸炎や慢性疾患が吐き気を引き起こすことがあります。
対策:
- 定期的な健康診断
- 異常があれば早急に相談
8.ストレス
原因: 環境の変化や大きな音、新しいペットなどがストレスとなり、嘔吐を引き起こすことがあります。
対策:
- ストレス軽減のための環境整備
- 遊びの時間や環境エンリッチメント
9.便秘
- 原因: 便秘が原因で消化不良を起こし、嘔吐することがあります。
- 対策:
- ・水分補給の促進
- ・運動の増加
- ・食物繊維を含むフードの選択
2. 猫が餌を吐いた時にチェックすべきポイント
- 1.嘔吐物の状態:
- 未消化のフード、毛玉、異物、色や匂いをチェックして原因を把握します。
- 2.吐いたタイミング:
- 食後すぐや数時間後、特定の状況での嘔吐を確認します。
- 3.吐いた後の様子:
- 吐いた後の元気さ、行動の変化、食欲や水分摂取を観察します。
- 4.吐いた回数:
- 一度だけか、繰り返しているかを確認します。
- 5.その他の症状:
- 下痢や便秘、体重減少、発熱、痛み、呼吸の状態、脱水症状をチェックします。
- 6.その他の要因:
- 環境変化や異物摂取、ワクチン接種や投薬の状況、外出の有無、多頭飼いの場合の症状を確認します。
3. 動物病院に行くべき危険な嘔吐と疑われる病気
- 1.頻繁な嘔吐:
- 疑われる病気: 慢性胃腸炎、胃腸閉塞、寄生虫感染
- 2.血液を伴う嘔吐:
- 疑われる病気: 胃潰瘍、腫瘍、異物摂取による内出血
- 3.異物を吐く:
- 疑われる病気: 異物誤飲による腸閉塞
- 4.泡や透明な液体を吐く:
- 疑われる病気: 急性膵炎、腎不全、胃腸障害
- 5.緑色や黄色い胆汁を吐く:
- 疑われる病気: 胆管閉塞、肝臓疾患
- 6.体重減少や脱水を伴う嘔吐:
- 疑われる病気: 腎不全、肝不全、糖尿病、腫瘍
- 7.突然の激しい嘔吐:
- 疑われる病気: 中毒
4. 猫が吐いた後の食事法・注意点
- 1.嘔吐直後の絶食:
- 12〜24時間程度の絶食を推奨。
- 2.水分補給の注意:
- 少量ずつ頻繁に水を与え、脱水を防ぐ。
- 3.少量で消化の良い食事:
- ウェットフードや消化に優しい療法食を少量ずつ与える。
- 4.フードの種類を変更しない:
- 普段のフードを選び、急な変更は避ける。
- 5.複数回に分けて少量ずつ与える:
- 1日4〜6回に分けて食事を提供。
- 6.ゆっくりと通常の食事に戻す:
- 徐々に通常の食事量に戻す。