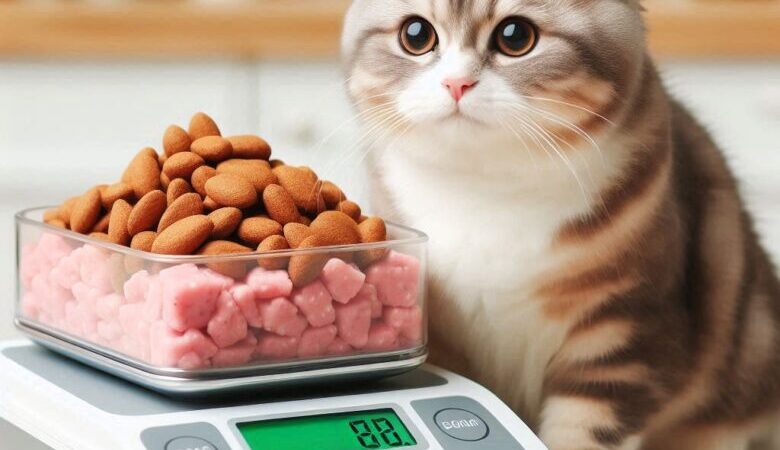

「うちの猫、太ってきたかも…」「でも、どのくらいあげればいいの?」
愛猫の健康を願うあなたへ。猫の食事量って、実はとても重要なんです。この記事では、猫の体重や年齢、活動量に合わせた適切なフード量の計算方法をわかりやすく解説します。
この記事を読めば、
- 猫の食事量を計算するための具体的な方法がわかります
- 猫の健康維持に必要な栄養バランスについて理解できます
- 愛猫の体重管理に役立つ情報が得られます
愛猫の健康的な毎日を送るために、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
猫の食事は、愛猫の健康を左右する大切な要素です。
フードのパッケージに書かれた量を参考にしている方も多いと思いますが、猫の個体差は大きく、一概に同じ量が良いとは限りません。
この記事では、RER(安静時エネルギー要求量)やDER(1日のエネルギー要求量)といった専門用語を噛み砕きながら、あなたの愛猫にぴったりのフード量を計算する方法を解説します。
BCS(ボディコンディションスコア)やMCS(筋肉量スコア)といった評価方法も取り入れ、より詳細な食事管理をサポートします。
愛猫の年齢や健康状態に合わせた食事の調整方法もご紹介しますので、ぜひ最後まで読んで、愛猫の健康的な食事管理に役立ててください。
愛猫の健康は、飼い主さんの愛情と正しい知識で支えられます。
この記事が、あなたと愛猫のより豊かな生活の一助となれば幸いです。
クリックできる目次
1. 猫のエサの量の基本
猫のエサの適量とは?
猫の健康を維持するためには、適量のエサを与えることが不可欠です。適量は猫の年齢、体重、活動量、健康状態によって異なります。
猫の適切なエサの量を決定するには、体重と必要エネルギー量の関係を理解することが重要です。この関係は、RER(Resting Energy Requirement:安静時エネルギー要求量)とDER(Daily Energy Requirement:1日のエネルギー要求量)を基に計算され、さらにBCS(ボディコンディションスコア)とMCS(筋肉量スコア)を用いて個々の猫の状態に合わせて調整されます。
1.エネルギー量の基礎知識
1.RER(安静時エネルギー要求量)
RERは、猫が安静時に必要なエネルギー量を表す指標です。体重と関係があり、以下の式で算出できます。
計算式:RER(kcal/日) = 70 × 体重(kg)の0.75乗
※電卓を使った計算方法
- 体重を入力: まず、猫の体重(kg)を入力します。
- 体重の0.75乗を計算: 体重を0.75乗します。例えば、体重が4kgの場合:
- 4^0.75 = 2.828
- 70を掛ける: 70を掛けます。
- 70 × 2.828 = 197.96
- 結果: RERは約198キロカロリー/日です。
※Excelを使った計算方法
- Excelを開く: Excelを開きます。
- セルに体重を入力: 例えば、セルA1に体重(kg)を入力します。
- 計算式を入力: 別のセルに以下の計算式を入力します。
=70 * (A1^0.75) - 結果を表示: Enterキーを押すと、RERが表示されます。

2 .DER(1日あたりのエネルギー要求量)
DERは、猫が1日に必要なエネルギー量を表す指標です。RERに、猫の活動レベルや年齢、健康状態などの係数を乗じて算出します。
計算式:DER(kcal/日) = RER × 係数
係数に関しては、下記の表を参考にして下さい。
係数の目安
| 状態・活動レベル | 係数 |
|---|---|
| 成猫(維持期) | 1.0~1.2 |
| 室内猫 | 1.0~1.2 |
| 活動的な成猫 | 1.2~1.4 |
| 減量を必要とする猫 | 0.8~1.0 |
| 成長期の子猫(0~4ヶ月) | 2.5~3.0 |
| 成長期の子猫(4~12ヶ月) | 2.0~2.5 |
| 妊娠中の猫 | 1.6~2.0 |
| 授乳中の猫 | 2.0~6.0 |
| 高齢猫(7~11歳まで) | 1.0~1.2 |
| 超高齢猫(11歳以上) | 0.8~1.1 |
猫のカロリー必要量:AAFP栄養ガイドライン
RERとDERの計算:WSAVA(世界小動物獣医学協会)
BCSとMCSの評価:AAHA(米国動物病院協会)
※この表の数値に振れ幅がある理由は、猫の個体差や生活環境、活動レベルなどによりエネルギー必要量が異なるためです。授乳中の猫の数値の振れ幅が特に大きいのは、子猫の数や授乳期間によるエネルギー消費の違いを反映しています。
例:体重3kgで活発な成猫の場合
- RER = 70 × 3kg^0.75 = 160kcal/日
- 係数 = 1.2
- DER = 160kcal/日 × 1.2 = 192kcal/日
3.体重別RERとDERの表
体重に基づいて、RERとDER(活動レベル別)が分かるように、計算して、表にまとめてありますので、ご自身の猫ちゃんの体重に合った1日のカロリー量を探してみて下さい。
※単位は、RER,DERともに(キロカロリー/日)です。
| 体重 (kg) | RER (㎉/日) | DER (維持期) | DER (室内猫) | DER (活動的) | DER (減量中) | DER (妊娠) | DER (授乳) | DER (高齢) | DER (超高齢) |
| 1kg | 70 | 70~84 | 70~84 | 84~98 | 56~70 | 112~140 | 140~420 | 70~84 | 56~77 |
| 2kg | 118 | 118~141 | 118~141 | 141~165 | 94~118 | 188~235 | 235~706 | 118~141 | 94~129 |
| 3kg | 160 | 160~191 | 160~191 | 191~223 | 128~160 | 255~319 | 319~957 | 160~191 | 128~176 |
| 4kg | 198 | 198~238 | 198~238 | 238~277 | 158~198 | 317~396 | 396~1188 | 198~238 | 158~218 |
| 5kg | 234 | 234~281 | 234~281 | 281~328 | 187~234 | 374~468 | 468~1404 | 234~281 | 187~257 |
| 6kg | 268 | 268~322 | 268~322 | 322~376 | 215~268 | 429~537 | 537~1610 | 268~322 | 215~295 |
| 7kg | 301 | 301~361 | 301~361 | 361~422 | 241~301 | 482~602 | 602~1807 | 301~361 | 241~331 |
| 8kg | 333 | 333~400 | 333~400 | 400~466 | 266~333 | 533~666 | 666~1998 | 333~400 | 266~366 |
| 9kg | 364 | 364~436 | 364~436 | 436~509 | 291~364 | 582~727 | 727~2182 | 364~436 | 291~400 |
| 10kg | 394 | 394~472 | 394~472 | 472~551 | 315~394 | 630~787 | 787~2362 | 394~472 | 315~433 |
【注1】猫のカロリー必要量:AAFP栄養ガイドライン
【注2】RERとDERの計算:WSAVA(世界小動物獣医学協会)
【注3】BCSとMCSの評価:AAHA(米国動物病院協会)
※係数に振れ幅がある為、DER値も振れ幅が生じています。猫の個体差や生活環境、活動レベル、健康状態、環境要因などによりエネルギー必要量が異なるためです。授乳中の猫の数値の振れ幅が特に大きいのは、子猫の数や授乳期間によるエネルギー消費の違いを反映しています。

「体重に応じてエネルギー量が変わるなんて、知ってた?自分にぴったりのカロリーがわかると嬉しいニャ!」
4. エサの量の目安
猫に必要なエサの量は、DERとフードのカロリーによって算出できます。
飼いネコちゃんのDERを、上の表で当てはめて調べた後、与えたいフードのカロリーで割ります。
- エサ量(g/日) = DER(kcal/日) ÷ フードのカロリー(kcal/g)
例:体重3kgで室内飼いの成猫が、100gあたり400kcalのフードを食べる場合
- DER = 160kcal/日
- フードのカロリー = 400kcal/100g
- エサ量 = 160kcal/日 ÷ 400kcal×100g = 40g/日

2.体脂肪・筋肉とエサの量の関係
猫の個体差や健康状態、活動レベルなどを考慮する必要があり、BCS(ボディコンディションスコア)とMCS(マッスルコンディションスコア)を指標として活用することで、より適切なエサ量を調整することができます。
1 .BCS(ボディコンディションスコア)
BCS(Body Condition Score、体重状態スコア)は、猫の体脂肪量を評価するためのスコアリングシステムです。一般的に1から9のスケールで評価され、以下のように分類されます。
BCS 1-3: 痩せすぎ
- 1.非常に痩せている:
- ・肋骨、背骨、骨盤が容易に見えるか触れる。
・体脂肪がほとんどない。
・筋肉量が著しく減少。
- ・肋骨、背骨、骨盤が容易に見えるか触れる。
- 2.痩せている:
- ・肋骨と背骨が容易に触れるが、わずかに皮下脂肪が感じられる。
・腹部の収縮が目立つ。
- ・肋骨と背骨が容易に触れるが、わずかに皮下脂肪が感じられる。
- 3.やや痩せている:
- ・肋骨が簡単に触れるが、見た目には目立たない。
・腰のくびれがはっきりとしている。
・腹部が引き締まっている。
- ・肋骨が簡単に触れるが、見た目には目立たない。

BCS 4-5: 理想体重
- 4.やや痩せ気味:
- ・肋骨が容易に触れるが、皮下脂肪が少し感じられる。
・腰のくびれがはっきりしている。
・腹部が引き締まっているが、極端に収縮していない。
- ・肋骨が容易に触れるが、皮下脂肪が少し感じられる。
- 5.理想的:
- ・肋骨が触れられるが、薄い皮下脂肪が感じられる。
・腰のくびれがはっきりしている。
・腹部が引き締まっている。
- ・肋骨が触れられるが、薄い皮下脂肪が感じられる。
BCS 6-9: 肥満
- 6.やや太り気味:
- ・肋骨が触れるが、明らかな皮下脂肪が感じられる。
・腰のくびれが少し見えるが、はっきりしていない。
・腹部に軽い脂肪の蓄積がある。
- ・肋骨が触れるが、明らかな皮下脂肪が感じられる。
- 7.太っている:
- ・肋骨がかなり厚い皮下脂肪の下にあり、触れるのが難しい。
・腰のくびれがほとんど見えない。
・腹部に顕著な脂肪の蓄積がある。
- ・肋骨がかなり厚い皮下脂肪の下にあり、触れるのが難しい。
- 8.非常に太っている:
- ・肋骨が厚い皮下脂肪の下にあり、ほとんど触れない。
・腰のくびれが全く見えない。
・腹部に大量の脂肪の蓄積がある。
- ・肋骨が厚い皮下脂肪の下にあり、ほとんど触れない。
- 9.極度に太っている:
- ・肋骨が極めて厚い皮下脂肪の下にあり、全く触れない。
・腰のくびれが完全に失われている。
・腹部と全身に非常に多くの脂肪が蓄積している。
- ・肋骨が極めて厚い皮下脂肪の下にあり、全く触れない。

「お腹がぽっこりしてきたら、BCSで確認してもらえるのは助かるニャ。健康で元気でいたいから、きちんとケアしてほしいニャ!」

2.MCS(マッスルコンディションスコア
MCS(Muscle Condition Score、筋肉状態スコア)は、猫の筋肉量を評価するためのスコアリングシステムで、4段階で評価されます。MCSの評価は、触診によって行われます。
0.重度の筋肉減少
・骨の構造が非常に顕著に見える。
・筋肉が極度に減少し、骨が明らかに突き出ている。
・背骨、肩甲骨、骨盤の骨が簡単に触れることができる。
(エサの量の調整)
・高品質で高タンパク質のフードを提供し、集中的な筋肉回復をサポートします。
・獣医師の指導の下で、適切な運動プランを立てます。
1.中程度の筋肉減少
・骨の構造がはっきりと見える。
・筋肉が顕著に減少している。
・背骨、肩甲骨、骨盤が明確に触れることができる。
(エサの量の調整)
・高タンパク質のフードを選び、筋肉の回復をサポートします。
・適度な運動を取り入れ、筋肉の再生を促します。
2.軽度筋肉減少
・骨の構造がやや見え始める。
・筋肉が少し減少しているが、まだ全体的に適度な筋肉量が保たれている。
・背骨や肩甲骨、骨盤の一部が触れることができる。
(エサの量の調整)
・タンパク質の多いフードを提供し、筋肉量の維持を図ります。
・軽度な運動を増やし、筋肉の減少を防ぎます。
3.正常筋肉量
・骨の構造が容易に見えない。
・筋肉が適度に発達しており、背骨や肩甲骨、骨盤などの骨が感じられない。
・触れると適度な張りを感じる。
(エサの量の調整)
・現在のエサの量を維持し、バランスの取れた栄養を提供します。
・定期的な運動を続けて筋肉量を維持します。

「筋肉量チェック?運動不足がバレちゃうかも…」

3. BCSとMCSの評価
まず、猫ちゃんのBCSとMCSを評価しましょう。
- BCSの評価:体脂肪量に基づいて、猫の栄養状態を9段階で評価します。
・理想的なBCSは、肋骨が触れるけど目視できない状態(スコア5)です。
・BCSが低すぎると(スコア1~3)、栄養不足による健康問題のリスクが高まります。
・逆 に、BCSが高すぎると(スコア6~9)、肥満による糖尿病や関節炎などのリスクが高まります。 - MCSの評価:筋肉量に基づいて、猫の筋肉量を4段階で評価します。
・理想的なMCSは、背骨や肋骨が薄く覆われている状態です。(スコア3)
・MCSが低すぎると(スコア0~1)、筋力低下や免疫力低下などのリスクが高まります。
4.BCSとMCSに基づいたエサ量の調整
BCSとMCSの評価結果に基づいて、RER/DERで算出した1日必要エサ量を以下のように調整します。
● BCSが低い場合
・エサ量を10~20%増やす
・高カロリーフードを与える
・食事回数を増やす
● BCSが高い場合
・低カロリーフードを与える
・エサ量を10~20%減らす
※0.8~1.0の係数の選択が、実質的に10~20%の減量に相当します。
・係数1.0は通常の維持エネルギー量に相当し、これを基準とします。
・係数0.9は約10%の減量に相当します。
・係数0.8は約20%の減量に相当します。
したがって、BCSで太っていると評価された場合、まずは0.9(10%減)から始め、減量の進み具合を見ながら必要に応じて0.8(20%減)まで下げていくことが一般的です。
● MCSが低い場合
・高タンパク質フードを与える
・運動量を増やす
● MCSが高い場合
・低炭水化物フードを与える
・運動量を増やす
5.具体的な例
例1:5kg、避妊済みの成猫、活動レベルは中程度
・体重:5kg
・避妊済みの成猫
・活動レベル:中程度
・BCS:スコア4(やや太り気味)
・MCS:スコア2(筋肉量が少ない)
計算手順:
- 1.RERの計算:
RER=70×5の0.75乗=234kcal(キロカロリー) - 2.通常のDERの計算(中程度の活動レベルの係数1.2を使用):
DER=234×1.2=281kcal(キロカロリー) - 3.減量のための調整:
この猫はBCSスコア4で「やや太り気味」なので、減量が必要です。
減量を必要とする猫の係数は0.8~1.0の範囲を使用します。
中程度の減量を目指すなら、係数0.9を使用できます:
DER =281×0.9=252.9kcal(キロカロリー) - 4.筋肉量の考慮:
MCSスコアが2で筋肉量が少ないため、タンパク質の摂取量を増やしつつ、総カロリーを抑える必要があります。これは、高タンパク質・低カロリーのフードを選択することで対応できます。
※調整のポイント
・ BCSとMCSは定期的に評価し、必要に応じてエサの量を調整します。
・体重の変化だけでなく、活動量や全体的な健康状態も観察します。
・特殊な健康状態(妊娠、授乳、疾病など)がある場合は、獣医師に相談すると良いでしょう。

「減量中はエサの量を減らしてもらえるといいニャ。でも筋肉量が少ない時は、ちゃんと高タンパクなフードをもらいたいニャ!」
2.年齢別のフード量の違いについて

猫の年齢によるエサの量の違いは、主に成長、活動量、代謝の変化に基づいています。子猫期は急速な成長のため多くのエネルギーを必要とし、成猫期で安定し、高齢期に向けて緩やかに減少していきます。以下で詳しく説明します。
1. 成長期の子猫(0~4ヶ月)
係数:2.5~3.0
この時期の子猫は急速に成長し、骨や筋肉の発達が進むため、非常に高いエネルギーと栄養を必要とします。高い係数が示すように、体重当たりのエネルギー必要量は成猫の2.5~3倍にもなります。成長期の子猫は以下の理由で多くのエサが必要です。
- 急速な成長:体重が急激に増えるため、多くのカロリーが必要です。
- 高い活動量:好奇心旺盛で活動的なため、エネルギー消費が多いです。
- 発達中の臓器と組織:骨や筋肉、内臓が急速に発達するため、高タンパク質と高カロリーのエサが必要です。
2. 成長期の子猫(4~12ヶ月)
係数:2.0~2.5
この時期の子猫は成長がやや緩やかになりますが、依然として高いエネルギーが必要です。
- 成長の継続:0~4ヶ月に比べ成長速度は落ちるものの、まだ体重が増加し続けます。
- 適度な活動量:依然として活動的ですが、成猫に近づくにつれエネルギー消費が安定してきます。
- 性成熟: 性的成熟に向けた身体の変化にエネルギーを必要とします。
3. 成猫(維持期)
係数:1.0~1.2
成猫は成長が完了し、体重とエネルギー需要が安定します。この時期にはエネルギーの維持が主な目的となります。
- 安定した体重:成長が完了し、体重が安定しています。
- 適度な活動量:日常的な活動でのエネルギー消費を賄うためのカロリーが必要です。
- 健康維持:免疫力を維持し、病気を予防するためにバランスの取れた栄養が必要です。
※係数の幅は主に活動量の違いを反映しています。室内飼いの猫は1.0に近く、外出する活発な猫は1.2に近くなります。
4. 高齢猫(7~11歳まで)
係数:1.0~1.2
老化に伴い、運動量や代謝が低下し、必要なエネルギー量がさらに少なくなります。係数1.0~1.2は、成猫と同じ範囲ですが、肥満気味の場合は係数を低めに設定する必要があります。
- 代謝の低下:成猫に比べて代謝が緩やかに低下するため、エネルギー消費も減少します。
- 活動量の減少: 徐々に活動量が減少し始める猫もいます。
- 健康管理:老化に伴い、関節や内臓の健康をサポートする栄養素が重要になります。
※エネルギー必要量自体は減少傾向にありますが、栄養の質を上げて健康維持をサポートする必要があります。
5. 超高齢猫(11歳以上)
係数:0.8~1.1
超高齢猫はさらに代謝が低下し、エネルギー需要も少なくなります。係数が低下しているのはその為です。しかし、低すぎると栄養不足のリスクがあるため、個々の猫の状態に応じた細やかな調整が必要です。
- さらに低下する代謝:代謝が大きく低下し、エネルギー消費が少なくなります。
- 筋肉量の減少: 筋肉量が減少し、エネルギー消費が減ります。
- 活動量の大幅な減少: 多くの猫で活動量が顕著に減少します。
- 健康維持の難しさ:消化機能が低下し、特定の栄養素の吸収が難しくなることがあります。低カロリーで高栄養価のエサが必要です。
- 病気のリスク増加:年齢に伴い、腎臓病や関節炎などの慢性疾患のリスクが高まるため、これらを予防するための栄養が重要です。

これらの係数はあくまでも目安です。実際のエサの量は、個々の猫の体重、体型、健康状態、生活環境などを考慮して調整する必要があります。定期的な体重測定とボディコンディションスコア(BCS)のチェックを行い、適切なエサの量を維持することが、猫の生涯を通じての健康管理の鍵となります。

「子猫の時はたくさん食べられたのに、大人になったら減らされちゃうにゃん」
3. 特殊な状況におけるエサの量
1.肥満猫のエサの量
肥満猫の場合、通常の成猫よりもエネルギー摂取量を減らす必要があります。係数0.8~1.0は、この減量の必要性を反映しています。
肥満猫は、体内に余分な脂肪が蓄積されているため、成猫よりも少ないエネルギーで必要な活動を維持することができます。
係数0.8~1.0の幅は、猫の活動レベルや肥満度によって必要なエネルギー量に差があるためです。
- 係数0.8: 重度の肥満や急速な減量が必要な場合に使用
- 係数1.0: 軽度の肥満や緩やかな減量を目指す場合に使用
1.肥満猫のエサの量の計算方法
基礎代謝率(RER)の計算
- RERは、猫の体重(kg)を基に計算されます。一般的な計算式は以下の通りです。
RER=70×(体重(kg))0.75乗
例えば、5kgの猫の場合:
RER=70×(5)0.75乗≈234kcal/日
減量のためのエネルギー摂取量(DER)の計算
係数を用いて、減量のためのエネルギー摂取量を計算します。
例えば、係数を0.9とした場合:DER=RER×0.9
5kgの猫の場合:
DER=234×0.9≈211kcal/日
1日あたりの食事量(kcal)の計算
1日あたりの食事量(kcal) = DER÷食事中のエネルギー量(kcal/100g)
例えば、食事中のエネルギー量350kcal/100gの場合:
1日あたりの食事量(kcal) =211kcal/日÷350kcal×100g ≈60g/日 と計算できます。
2.実践的なエサの与え方
- ・正確な計量: デジタルスケールを使用し、1g単位で計量します。
- ・食事回数: 1日に2~4回に分けて与えることで、代謝を上げ、空腹感を軽減します。
- ・ダイエット用フードの活用: 低カロリーで栄養バランスの取れたダイエット用療法食を使用します。
- ・水分補給: ウェットフードを組み合わせるか、水を多く飲むよう促し、満腹感を高めます。
- ・おやつの管理: おやつは極力控え、与える場合は1日の総カロリーの10%以内に抑えます

「エネルギーを減らしてダイエット中だニャ。でも、美味しいダイエットフードで満足したいから、ちゃんと量を守ってね!」
2.妊娠中・授乳中の猫のエサの量

妊娠中や授乳中の猫は、通常の成猫に比べて著しく高いエネルギー要求があります。これは、胎児の発育や母乳の生産に必要なエネルギーが増加するためです。具体的に見ていきましょう。
1.妊娠中の猫の係数が高い理由(係数:1.6~2.0)
妊娠中の猫の係数が通常の成猫より高いのは、以下の理由によります:
- ・胎児の成長: 母猫の体内で発育する子猫たちにエネルギーが必要です。
- ・子宮と乳腺の発達: 出産に備えて、これらの組織が発達するためエネルギーを要します。
- ・代謝率の上昇: 妊娠によってホルモンバランスが変化し、基礎代謝率が上昇します。
- ・体重増加: 健康的な妊娠では、母猫の体重が15-20%程度増加します。この増加分の維持にもエネルギーが必要です。
- ・栄養素の貯蔵: 授乳期に備えて、体内に栄養を蓄えるためのエネルギーも必要となります。
2.授乳中の猫の係数が高い理由(係数:2.0~6.0)
授乳中の猫の係数が特に高いのは、以下の理由によります:
- ・乳汁生産: 母乳の生産には大量のエネルギーが必要です。母乳は高カロリー、高タンパクで、その生成には多大なエネルギーを要します。
- ・子猫の数: 係数の幅が大きいのは、主に子猫の数に依存します。子猫が多いほど、より多くの乳汁を生産する必要があるため、係数は高くなります。
- ・授乳の頻度と量: 新生子猫は頻繁に授乳を必要とし、成長とともに1回の授乳量も増えていきます。
- ・母猫の体温維持: 頻繁な授乳で体温が奪われるため、体温維持にも追加のエネルギーが必要です。
- ・母猫の回復: 出産後の身体の回復にもエネルギーを要します。
- ・子猫の成長段階: 生後間もない時期は係数が最も高く、子猫の成長に伴い徐々に低下していきます。
- ・母猫の体重維持: 授乳中は大量のエネルギーを消費するため、母猫自身の体重と健康を維持するのに多くのエネルギーが必要です。
3.具体的な係数選択
妊娠中や授乳中の猫にエサをあげる際に、係数の振れ幅が大きいことから、どの数値を使って計算すればよいか迷うかもしれません。以下に、具体的な指針を提供します。
妊娠中の猫(係数:1.6~2.0)
妊娠中の猫の適切な係数は、妊娠の段階によって変化します:
- 妊娠初期(1~3週目):1.6
- 妊娠中期(4~6週目):1.8
- 妊娠後期(7~9週目):2.0
※妊娠が進むにつれてエネルギー需要が増加するため、妊娠後期はより高い係数を用いることをおすすめします。
授乳中の猫
授乳中の猫のDER係数は2.0~6.0と非常に幅があります。これは、授乳中のエネルギー需要が子猫の数や授乳頻度によって大きく異なるためです。具体的な数値の選び方は以下の通りです:
- 少数の子猫(1~2匹): 2.0~3.0を使用
- 中程度の子猫の数(3~4匹): 3.0~4.0を使用
- 多数の子猫(5匹以上): 4.0~6.0を使用
※授乳中はエネルギー消費が非常に高くなるため、子猫の数が多い場合には上限に近い数値を使用する必要があります。

「授乳中はもっとたくさんのエネルギーが必要だニャ。子猫たちにたっぷりミルクをあげるために、ママもたくさん食べて元気を保つニャ!」
3.病気や健康状態に応じたエサの量

1. 獣医師の指導を受ける
まず、猫が病気や特定の健康状態にある場合、獣医師の指導を受けることが最も重要です。獣医師は猫の具体的な状態に基づいて、適切なエサの量や種類をアドバイスしてくれます。
2. エネルギー要求量(DER)の調整
猫のエネルギー要求量(DER)は、健康状態によって変わることがあります。
体重増加が必要な場合
体重が不足している猫や回復期の猫には、エサの量を増やす必要があります。この場合、DERを計算する際の係数を高めに設定します。例えば、成猫の維持期の係数1.0~1.2のうち、1.2に近い値を使用します。
慢性疾患がある場合
慢性疾患(例えば、腎臓病や糖尿病)の猫には、特定の栄養管理が必要です。これには、特定の栄養素の制限や追加が含まれることがあります。獣医師の指導に従い、適切なエサの量と種類を選びます。
同じ疾患でも、猫の年齢、体型、症状の程度によってエサの量は変わります。
3. エサの種類と質
病気や健康状態に応じて、エサの種類や質も重要です。例えば、腎臓病の猫には低タンパク質のエサが推奨されることがあります。また、消化器系の問題がある猫には、消化しやすいエサが適しています。
4. 定期的なモニタリング
猫の体重や健康状態を定期的にモニタリングし、必要に応じてエサの量を調整します。体重の変化や健康状態の改善・悪化に応じて、エサの量や種類を見直すことが重要です。
※病気の猫のエサの量を決めるのは複雑なプロセスです。必ず獣医師の指導の下で、個々の猫に合わせた適切な栄養管理を行ってください。定期的な健康チェックと、状態の変化に応じた柔軟な調整が、愛猫の健康管理の鍵となります。

「病気の時も、適切なエサでしっかりサポートしてもらいたいニャ。お医者さんと相談して、ぴったりのご飯を見つけてね!」
4. エサの量に関するよくある悩みと解決策

1.猫が頻繁におねだりするため、適切な量が分からず与えすぎてしまう。
解決策:
- 定時給餌を実践し、1日の総量を2-4回に分けて与える
- おやつは全体の10%以内に抑える
- おねだり時は遊びで気を紛らわせる
- 自動給餌器の利用を検討する
2.パッケージに書かれた推奨量を与えても、猫が太ってしまう。
解決策:
- 猫の年齢、体格、活動量に基づいてRERを計算し、適切な係数を掛ける
- 体重と体型(BCS)を定期的にチェックし、調整する
- 活動量に合わせて給餌量を増減する
- 獣医師に相談し、個別の給餌プランを立てる
3. 複数の猫を飼っている場合、エサの管理が難しいです。
解決策:
- 部屋を分けるなど、各猫に専用の食事場所を設けることで、エサの量を個別に管理しやすくなります。
- 複数の自動給餌器を使うことで、各猫に適切な量のエサを与えることができます。
- 各猫の食事行動を観察し、必要に応じてエサの量を調整します。
4.季節によって猫の食欲や必要量が変化し、適切な量が分からない。
解決策:
- 冬場は代謝が上がるため、10-15%程度増量を検討
- 夏場は活動量が下がるため、やや減量を考慮
- 季節の変わり目には体重をこまめにチェックし、調整する
- 室温管理で極端な変化を抑える
5.エサの量を減らしても体重が減らない。
解決策:
- 総カロリー摂取量を確実に把握し、おやつも含めて計算する
- 低カロリーで満腹感のあるダイエットフードに切り替える
- 運動量を増やす工夫をする(おもちゃ、キャットタワーなど)
- 体重の10%減量を目標に、ゆっくりと時間をかける
5. エサの量を管理するためのツールとテクニック

猫の健康維持に欠かせない食事管理。適切な量の食事を与えることは、猫の肥満予防や様々な健康問題を防ぐために重要です。以下に、猫の食事量を正確に管理するためのツールやテクニックをご紹介します。
1. デジタルフードスケール
デジタルフードスケールを使うことで、猫のエサの量を正確に測ることができます。目分量ではなく、正確なグラム数を計測することで、適切なカロリー管理が可能になります。特に減量や体重維持が必要な猫には有効です。
2. フードディスペンサー(自動給餌器)
フードディスペンサーは、設定した時間と量に基づいて自動的にエサを出してくれる装置です。これにより、飼い主が不在でも一定量のエサを与えることができます。また、過食を防ぐのにも役立ちます。
3. スマホアプリ
- 食事記録アプリ: 毎日与えたフードの種類や量を記録することで、食事のバランスを把握できます。
- 体重管理アプリ: 体重の変化をグラフ化し、体重管理をサポートします。
4. 食事記録ノート
手書きのノートやデジタルノートを使って、毎日の食事量や体重の変化を記録することも有効です。これにより、長期的な変化を把握しやすくなります。
5. 定期的な体重測定
定期的に猫の体重を測定し、エサの量を調整することが重要です。体重計を使って、週に一度程度の頻度で測定すると良いでしょう。
6. 獣医師のアドバイス
最後に、獣医師のアドバイスを受けることも忘れずに。専門家の意見を参考にすることで、より適切なエサの管理が可能になります。
これらのツールやテクニックを活用して、猫の健康を維持し、適切な体重管理を行いましょう。読者の皆さんも、ぜひ試してみてください。

「自動給餌器で決まった時間にご飯が出てくるのは、すごく便利だニャ!これでお腹が空かないように管理してもらえるんだね。」
6.まとめ

猫のエサの量を適切に管理することは、健康維持に欠かせない要素です。本記事では、猫のエサの量を決定するための基本的な知識と手順を紹介しました。以下はその要点です。
1.エネルギー要求量の計算
- RER(安静時エネルギー要求量): 体重を基に計算される基礎エネルギー量。
計算式:RER(kcal/日) = 70 × 体重(kg)の0.75乗 - DER(1日あたりのエネルギー要求量): RERに活動レベルや年齢、健康状態の係数を乗じて算出。
計算式:DER(kcal/日) = RER × 係数
2.体重別RERとDER
- 猫の体重に基づいてRERとDERを計算し、それに基づいて1日のカロリー量を決定。
体重に基づいて、RERとDER(活動レベル別)が分かるように、計算して、表にまとめてあります。
3.エサの量の目安
- DERとフードのカロリーを基にエサの量を計算。
エサ量(g/日)= DER(kcal/日) ÷ フードのカロリー(kcal/g)
4.体脂肪・筋肉とエサの量の関係
- BCS(ボディコンディションスコア): 体脂肪量を評価し、1から9のスケールで評価。
- MCS(マッスルコンディションスコア): 筋肉量を4段階で評価し、触診によって行う。
5.年齢別のフード量の違い
- 子猫期は多くのエネルギーを必要とし、成猫期で安定し、高齢期に向けて緩やかに減少。
6.特殊な状況におけるエサの量
- 肥満猫: 減量が必要な場合、通常の成猫よりもエネルギー摂取量を減らす。
- 妊娠中・授乳中の猫: 高いエネルギー要求があり、係数を高めに設定。
- 病気や健康状態: 獣医師の指導を受け、エサの量や種類を調整。
これらのポイントを基に、猫の健康を維持するために適切なエサの量を決定することができます。定期的なモニタリングと調整を行い、猫の個々の状態に合わせた適切な栄養管理を行うことが重要です。